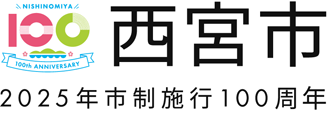介護保険負担限度額の認定(居住費・食費の軽減制度)
更新日:2025年12月17日
ページ番号:32925693
制度概要
次の要件を満たす方は、各段階に応じて1日あたりの食費・居住費(滞在費)の負担限度額が決められています。負担限度額を超える費用は介護給付費として施設に支払われます。制度の利用をご希望の場合は、下記のとおり申請書を提出してください。承認された場合は、申請書受付月の1日から適用の証を送付します。
制度の要件と利用者負担段階(次の2つの要件を満たす場合)
| 利用者負担段階 | 非課税等要件 | 資産要件(左欄の場合に右欄に示す金額以下であること) | |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者 | なし | |
| 第2段階 | 世帯の全員が市民税非課税(世帯を分離している配偶者を含む) | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80.9万円以下 | 預貯金等の合計が650万円(夫婦の場合はあわせて1,650万円)以下 |
| 第3段階(1) | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額80.9万円超120万円以下 | 預貯金等の合計が550万円(夫婦の場合はあわせて1,550万円)以下 | |
| 第3段階(2) | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が年額120万円超 | 預貯金等の合計が500万円(夫婦の場合はあわせて1,500万円)以下 | |
※年金収入額には老齢年金などの課税年金だけではなく、非課税年金(遺族年金・障害年金)も含む。
※その他の合計所得金額は、譲渡所得に係る特別控除を除く。
※その他の合計所得金額に給与所得が含まれている場合、所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除した後の金額を用いる。
※65歳未満の人は、収入等に関係なく、預貯金等の合計は1,000万円(夫婦は2,000万円)以下。
1日あたりの負担限度額(上記要件で決まった利用者負担段階を参照)
| 利用者負担段階 | 食費 | 居住費(滞在費) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多床室 (特養等) | 多床室 (老健等) | 従来型個室 | 従来型個室 | ユニット型個室的多床室 | ユニット型個室 | ||
| 第1段階 | 300円 | 0円 | 0円 | 380円 | 550円 | 550円 | 880円 |
| 第2段階 | 390円 (600円) | 430円 | 430円 | 480円 | 550円 | 550円 | 880円 |
| 第3段階 (1) | 650円 (1,000円) | 430円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
| 第3段階 (2) | 1,360円 | 430円 | 430円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 |
※短期入所(ショートステイ)を利用した場合、食費の負担限度額は( )内の金額。
申請方法
提出書類
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 本人と配偶者(内縁含む)の保有資産額を証明する書類全て(下表参照)
- 登記事項証明書等の代理権の存在を確認できる書類(成年後見人等が申請する場合)
- マイナンバーを確認するための書類(詳細はこちら)
※書類はハサミなどで枠に沿って切っていただく必要はありません。
※生活保護を受給の場合、2の書類の提出は不要です。
| 保有資産の種類 | 必要な提出書類 |
|---|---|
| 預貯金(普通・定期・外貨等) | 預貯金通帳で次のことが分かる箇所の写し全て
|
| 有価証券(株式・国債・社債等) | 証券会社、銀行等の評価額が分かるものの写し |
| 投資信託 | 銀行、信託銀行、証券会社等の評価額が分かるものの写し |
| 金・銀等(積立購入を含む) | 購入先の銀行等の評価額が分かるものの写し |
| 現金(タンス預金等) | 自己申告のため不要 |
| 負債(借入金・住宅ローン等) | 借用証書の写し |
※通帳記帳するなど申請日時点で最新の状態のものを提出してください。
※生命保険、自動車、時価評価額の把握が困難なもの(宝石等)については提出不要です。
申請書にマイナンバーを記載した場合は、番号確認及び本人確認(代理権確認)のため次の書類を申請の際に提示ください。郵送の場合は、コピーを添付して提出してください。提示(提出)書類のより詳しいことについては、「![]() 本人確認の措置(内閣府資料)(PDF:1,189KB)」をご覧ください。
本人確認の措置(内閣府資料)(PDF:1,189KB)」をご覧ください。
なお、マイナンバーの記載や書類の提示(提出)が困難な場合は、マイナンバーは未記入とし、書類の提示(提出)も必要ありません。
提示(提出)書類
- マイナンバーカード(券面の表と裏)
(代理人が申請する場合は併せて)
- 代理人の顔写真付き本人確認書類(官公署が発行したもの)
※顔写真がないものは2点の提示が必要です。なお、健康保険資格確認証のコピーを郵送する場合は保険者番号・記号番号をペンで塗りつぶす等見えない状態で送付してください。 - 代理権が確認できるもの
成年後見人等の場合 登記事項証明書、その他法定代理人であることを証明する書類
その他代理人の場合 委任状
※同一世帯員の場合は不要
提出先
郵送の場合 西宮市六湛寺町10-3 西宮市高齢介護課宛てに郵送してください。
窓口の場合 西宮市高齢介護課(市役所本庁舎1階11番窓口)へお越しください。
対象外の方でも軽減が認められる特例
市民税課税の高齢者夫婦等の世帯であっても、一方が介護保険施設に入所することで在宅での生活が困難とならないように、特例として食費・居住費の一部を軽減する制度があります。該当する場合は、高齢介護課までお問合せください。
制度の要件(次の要件を全て満たす場合)
- その世帯に属する構成員(世帯分離している配偶者を含む)の数が2人以上であること。
- 介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階(全額自己負担)の食費・居住費を負担すること。
- 世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)の年金収入額とその他の合計所得金額を合計した額から、施設の利用者負担(食費・居住費を含む)の年額見込みの合計額を除いた額が80.9万円以下になること。
- 世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)の預貯金等の合計が450万円以下であること。
- 世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)について、日常生活に供する資産以外に活用できる資産のないこと。
- 世帯全員(世帯分離している配偶者を含む)について、介護保険料を滞納していないこと。
申請書ダウンロード
申請書様式
案内・記入例
説明動画
関連リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()