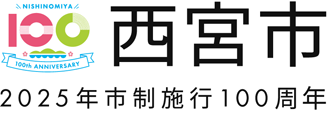介護保険を使ってサービスを利用するためには(要介護認定手続き等について)
更新日:2026年1月9日
ページ番号:97175112
1.要介護認定について
介護保険を使ってサービスを利用するためには、「要介護(要支援)認定」を受ける必要があります。(以下「要介護認定」とします)
病気や怪我・物忘れなどで、家事や入浴、排泄といった身の回りのことに支障が出始め、介護保険サービスの利用が必要になった時に申請を検討してください。
要介護認定の状態区分は、要支援1・2(要支援状態)、要介護1~5(要介護状態)の7段階に区分されます。
※介護認定には有効期間があります。(新規申請の場合:3か月~12か月)
※日常生活が自立していると判断された場合は、非該当の結果が出る可能性があります。
2.要介護認定の対象者
(1)65歳以上の人(第1号被保険者)
(2)40歳から64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)※
※加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する16の疾病(特定疾病)により、介護(支援)が必要な方が対象となります。あらかじめ、主治医に特定疾病に該当する病名で意見書を作成してもらえることを確認した上で、申請書類をご提出ください。
3.要介護認定の手続きについて
申請
以下の書類を高齢介護課へご提出ください。(書類をインターネットや窓口で入手することが困難な方は、高齢介護課へお電話ください。0798-35-3133・3348)各支所、サービスセンターでは提出できません。
申請の流れについては![]() リーフレット「要介護認定について」(PDF:1,980KB)もご参照ください。
リーフレット「要介護認定について」(PDF:1,980KB)もご参照ください。
![]() (1)65歳以上の人(第1号被保険者)申請書類一式(PDF:2,582KB)
(1)65歳以上の人(第1号被保険者)申請書類一式(PDF:2,582KB)
![]() (2)40歳から64歳の人(第2号被保険者)申請書類一式(PDF:2,888KB)
(2)40歳から64歳の人(第2号被保険者)申請書類一式(PDF:2,888KB)
※介護保険被保険者証を紛失された方は、![]() 介護保険資格異動届兼交付等申請書(PDF:293KB)もご提出ください。
介護保険資格異動届兼交付等申請書(PDF:293KB)もご提出ください。
※成年後見人等の法定代理人が申請を行う場合は、3か月以内に発行された登記事項証明書もしくはその他法定代理人であることを証明する書類のコピーもご提出ください。
●申請にあたっての注意事項
申請を受け付けてから認定結果の通知まで、30日程度かかります。要介護認定の結果が出るまでに、早急にサービスを利用しなければならない場合は、西宮市高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)または居宅介護支援事業者へ連絡してください。(利用には条件があります)
要介護認定の有効期間開始日は、申請区分によって異なりますのでご注意ください。
新規、区分変更、要支援・要介護者新規は、後述の「申請日について」で判断した申請日が有効期間開始日です。
更新は、前回の認定有効期間終了日の翌日が有効期間開始日です。※更新申請は前回認定の有効期間終了日までに行ってください。前回認定の有効期間終了日を過ぎて申請した場合は、新規申請とみなし、今回の申請日が認定有効期間開始日となります。
●申請日について
申請日は、原則として高齢介護課が申請書を受理した日となります。
ただし、区分変更及び要支援・要介護者新規で、申請書記載の申請日から5開庁日以内に高齢介護課が申請書を受理した場合は、申請書記載の申請日のとおりとします。また、申請書記載の申請日より前に暫定的に介護サービスを利用している場合は、暫定サービスの利用開始日を申請日とします。
40歳から64歳の人(第2号被保険者)の医療保険加入状況の確認方法について
40歳から64歳の人(第2号被保険者)は、申請書の「医療保険欄」「特定疾病番号」「マイナ保険証についてのチェック欄」を必ずご記入ください。
●マイナ保険証を持っている人
マイナンバーを用いた情報連携(市と情報を保有する機関とで連携すること)にて医療保険加入状況の確認を行います。
●マイナ保険証を持っていない人
「資格確認証」のコピーをご提出ください。
訪問調査
調査員があらかじめ電話で日時をお約束して訪問し、ご本人の心身の状態について調査を行います。
※調査の際にはできるだけご家族の立会をお願いします。
●訪問調査時における新型コロナウイルス感染症予防のご協力のお願い
訪問調査時の新型コロナウイルス感染リスクを低減するため、ご理解とご協力をお願いします。
詳しくは「![]() 要介護認定調査における感染症予防のために(PDF:57KB)」をご参照ください。
要介護認定調査における感染症予防のために(PDF:57KB)」をご参照ください。
主治医意見書
市から主治医に対して医学的な見地による意見書の提出を依頼します。主治医には意見書を作成してもらえるかどうか、事前に確認しておいてください。主治医から受診を求められた場合には、指示に従ってください。
介護認定審査会による判定
訪問調査項目および主治医意見書のうち一部の項目に基づく一次判定、訪問調査時に調査員が聞き取りした事項(特記事項)、および主治医意見書全体の記載内容に基づいて審査し、最終の判定(二次判定)を行います。
審査会の委員は医師、歯科医師、保健師、社会福祉士、薬剤師など保健・医療・福祉に関する専門家4人によって構成されています。
認定結果の通知
認定の結果を、新しい介護保険被保険者証に記載してお送りします。被保険者証には、このほか認定の有効期間、利用できるサービスの上限(区分支給限度基準額)などが記載されています。
なお、要介護認定はどの程度の介護を必要とするかについての状態を示す区分ですので、必ずしも医学的な症状の重さや障害の重さと一致するものではありません。
4.サービスの利用の始め方
要支援1・要支援2と認定された方
予防給付や介護予防・日常生活支援総合事業の利用ができます。利用される場合は、西宮市高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)に相談してください。
要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5と認定された方
介護給付が利用できます。居宅サービスを利用する際は、居宅介護支援事業者に相談してください。(西宮市内の居宅介護支援事業者一覧は「介護・障害福祉サービス事業者情報(外部サイト)![]() 」内の「介護・障害福祉サービス事業者一覧の閲覧」をご参照ください)
」内の「介護・障害福祉サービス事業者一覧の閲覧」をご参照ください)
施設サービスの利用にあたっては介護保険施設に相談してください。(西宮市内の介護保険施設一覧は「介護・障害福祉サービス事業者情報(外部サイト)![]() 」内の「介護・障害福祉サービス事業者一覧の閲覧」をご参照ください)
」内の「介護・障害福祉サービス事業者一覧の閲覧」をご参照ください)
非該当と認定された方
認定の結果が「非該当」と判定された方も、基本チェックリスト等により事業対象者に該当された場合など「介護予防・日常生活支援総合事業」が利用できる場合があります。「介護予防・日常生活支援総合事業」のご利用を希望される場合は、西宮市高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)に相談してください。
交通事故等が原因で介護保険サービスが必要になった方
別途、高齢介護課へお申し出ください(0798-35-3048)。(詳細はこちら)
5.認定の更新(認定有効期間が満了する場合)
要介護認定には認定の有効期間が設定され、この有効期間内に限り、介護保険のサービスを利用できます。認定有効期間の満了後も引き続きサービス利用を希望する場合は、要介護認定の更新申請を行ってください。なお、更新の申請は有効期間が満了する60日前から可能です。更新申請をすると、改めて訪問調査と主治医意見書の内容により判定が行われます。
介護保険のサービスをご利用中の場合は、担当のケアマネジャーと相談しながら更新申請を行って下さい。介護保険のサービスを利用されていない場合は、「3.要介護認定の手続きについて」をご参照のうえ、ご自身で更新申請を行ってください。
※新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについては、令和6年3月31日をもって終了いたしました。
6.認定区分の見直し(状態が大きく変わった場合)
要介護認定区分の「変更」の申請をすることができます。要介護・要支援認定はあくまで調査時点での状態を示すものですから、その後の経過によっては状態が変わることもあります。そのような時は、認定の有効期間の途中でも認定区分の変更申請が可能です。変更申請をすると、改めて訪問調査と主治医意見書の内容により判定が行われます。
介護保険のサービスをご利用中の場合は、担当のケアマネジャーと相談しながら変更申請を行ってください。介護保険のサービスを利用されていない場合は、「3.要介護認定の手続きについて」をご参照のうえ、ご自身で変更申請を行ってください。
7.転出、転入について
●他の市町村に転出する場合
西宮市で要介護認定を受けた方が転出される場合、現在有効な要介護度を転出先の市町村で引き継ぐことができます。
転出される際、高齢介護課にて現在の要介護度等を記載した「受給資格証明書」を発行します。受給資格証明書は転入日から14日以内に転出先の介護保険担当課へ提出してください。なお、転出先の住所が住所地特例施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム等)の場合には引き続き西宮市の介護保険被保険者となります。
※住所地特例についての詳細はこちらをご参照ください。
●他の市町村から転入した場合
転入日(新住所地に住み始めた日)から14日以内に、前住所地で発行された「受給資格証明書」を添えて、高齢介護課の窓口で認定申請をしてください。前住所地の認定を引き継いで、新しい介護保険被保険者証をお送りします。
なお、転入日から14日を過ぎると、前住所地の認定は継続できず新規申請をしていただくことになります。この場合は、転入日から新規申請日までの間に介護サービスの利用があると全額自己負担になりますのでご注意ください。
訪問看護やリハビリを現在ご利用されている方はご注意ください
現在医療保険で、介護保険の「訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ」に相当するサービスのうちいずれかを利用している場合は、事前に利用中の医療機関もしくは西宮市高齢者あんしん窓口へ連絡し、介護認定の申請中であることを必ず伝えてください。
これらのサービスについては、介護保険が優先して適用されるため、必要な手続きをせずサービスを利用した場合に本人負担額が10割になることがあります。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
高齢介護課
西宮市六湛寺町10-3 西宮市役所本庁舎3階
電話番号:0798-35-3133・3348
ファックス:0798-35-6658