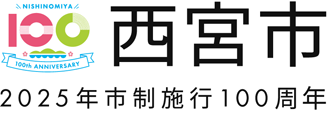プロから学ぶ人形劇おとな講座
更新日:2025年3月12日
ページ番号:79053585
人形劇団クラルテを講師にお迎えして実施する「人形劇おとな講座」を開講します
開催概要
「人形劇、はじめてみませんか Part2」
人形劇団クラルテの演出を手掛ける東口次登さんを講師にお迎えして、人形劇講座を開催します。「はじめまして」でも大丈夫、グループを作って、自分たちが作った人形で、おはなしを作って、演じてみましょう。
日時
令和7年(2025年)4月13日(日曜日)13時00分~16時00分
※13時00分開場、13時15分開始予定
※終了時間はかたずけ時間も含む
会場
西宮市大学交流センター講義室2(アクタ西宮東館6階)
対象
高校生以上の初心者
講師
人形劇団クラルテ 東口次登さん
持ち物
人形をお持ちの方はご持参ください。
お持ちでない方には貸出いたします。
※今回の講座では人形の製作は行いません。
定員
20名 ※多数の場合は抽選
申込方法
- インターネット申請
- ハガキ
イベント名(人形劇おとな講座)、氏名、ふりがな、電話番号、メールアドレス、参加者数を書き、西宮市文化スポーツ課(文化担当)〒662-8567六湛寺町10-3まで
申込締切
4月2日(水曜日) 必着
人形操り発祥の地 西宮
室町時代、西宮神社の近辺には傀儡子(くぐつし)と言われる人々が住んでいました。彼らはえびす様が鯛を釣るという素朴で信仰的な内容の人形まわしで国々を回り、えびす様の札を売り福を祈りました。傀儡子たちのこの芸能は「えびすかき」と呼ばれ、庶民文化が発展した時代に、えびす信仰とともに民衆に広く受け入れられました。芸に秀でたものは能を人形に舞わせて人気を博し、西宮の傀儡子が宮中に招かれたという記録が残っています。
江戸時代には、当時流行していた浄瑠璃と人形操りが結びつき、技芸がさらに磨かれて舞台芸術としての人形浄瑠璃が生まれ、後に文楽にも発展しました。
傀儡子たちが厚く信仰した人形操りの祖、百太夫をおまつりする神社が西宮神社の境内にあります。人形浄瑠璃や文楽にいたるルーツを持つ西宮は、人形操り発祥の地と言われています。