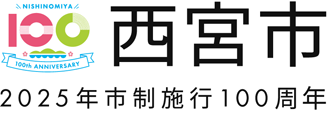保険料を納めることが困難なとき(申請免除、納付猶予)
更新日:2025年8月8日
ページ番号:30632088
(制度)概要
申請免除
失業や所得が低いなどの理由で国民年金保険料の納付が困難なときには、申請して認められると保険料の納付が免除される申請免除制度があります。免除を受けるためには、日本年金機構による所得審査があり、申請者本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得が一定の基準額以下であることが必要です。
納付猶予(50歳未満の方)
納付猶予制度は、国民年金保険料の納付が困難な50歳未満の第1号被保険者の方を対象とした制度です。申請免除とは異なり世帯主の所得は審査対象とならず、申請者本人と配偶者の所得が一定の基準額以下であれば、保険料の納付が猶予されます。
手続きの流れ
必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
※1 失業等の特別の事情がある場合は、「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」「離職者支援資金の貸付決定通知書」など、離職の事実を証明できる公的機関が発行する書類を提出してください。
※2 別世帯の配偶者がいる場合、配偶者の個人番号の記入が必要です。
※3 所得審査の対象者の中で一定以上の所得がある方については、所得の申告が必要です。
※4 その他の書類が必要になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
受付窓口及び受付時間(平日)
- 市役所医療年金課、各支所、市民サービスセンター
午前9時から午後5時まで
※正午から午後1時までは、支所、サービスセンターで受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
- アクタ西宮ステーション
午前9時から午後7時まで
※午後5時以降は、関係機関が業務を行っていない等の理由により受付できない場合があります。
詳しくは直接お問合せください。
手続きは、スマートフォン等を使用したマイナポータルによる電子申請や、郵送でも可能です。詳細は日本年金機構のホームページ「電子申請(マイナポータル)」(外部サイト)![]() 「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト)
「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」(外部サイト)![]() をご確認ください。
をご確認ください。
注意事項
- 市で受理した申請書は、日本年金機構へ送付します。審査の結果は、後日、直接本人あてに日本年金機構から郵送されます。審査結果が届くまでには概ね2ヵ月かかります。
- 申請免除、納付猶予の申請をした場合でも、保険料の納付書は送付されます。申請後に保険料を納付され、後日免除等が承認された場合は、原則として保険料は還付されます。
- 口座振替をしている場合は、口座振替辞退申出書を金融機関または西宮年金事務所にご提出いただくと、振替はとまります。万が一、申請後に振替され、後日免除等が承認された場合は、原則として保険料は還付されます。
- 還付すべき保険料が発生した場合であって、未納期間がある場合は、当該未納期間に還付すべき保険料が充当されることがあります。
- 申請免除、納付猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めること(追納)ができます。(ただし、2年度を過ぎて追納する場合は加算金がつきます。)