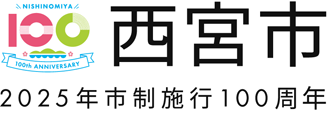申込資格
更新日:2025年10月16日
ページ番号:16810302
申し込み資格について
市営住宅に応募される方は、次の1~6のすべての条件を満たしている必要があります。
※申込資格は公募の選考方式(<抽選方式><ポイント方式>)を問わず共通です。
※<抽選方式>申し込み時の『優先枠』の資格については下の『市営住宅募集における優先枠について』をご覧ください。
リンク
1.申込の本人が西宮市内に住んでいるか、勤務等をしている方
募集開始日現在、西宮市内に居住しているか、勤務場所を有する方。(住民票又は在職証明書等で事実確認できる方。)
西宮市営住宅に居住している同居人が申し込む場合は、募集開始日現在、入居しようとする者全員の同居承認をすでに受けていることが必要です。
離婚された方は、同居承認者ではなくなるため現住宅に居住のまま申し込みできません。
市営住宅の名義人およびその配偶者(内縁含む)は申し込みできません。
※下記に該当する方は、市外に居住されている場合でも申し込みできます。
(A)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方。
(B)配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手方からの暴力を受けた方で、次のいずれかに該当する方。
- 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号(第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護、同法第5条(第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方(女性自立支援施設等の証明が必要)。
- 配偶者暴力防止法第10条第1項は第10条の2(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による退居命令又は接近禁止命令の申立てを行った方で、裁判所がした当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方(裁判所からの保護命令通知書等の写しが必要)。
- 女性相談支援センター又は配偶者暴力相談支援センターから配偶者からの暴力を受けている旨の証明を受けている方で当該証明から5年を経過していない方(女性相談支援センター又は配偶者暴力相談支援センターの証明が必要)。
- 配偶者暴力対応機関、行政機関又は関係機関と連携して被害者支援を行っている民間支援団体において、配偶者からの暴力を理由に避難している旨の確認を、国土交通省住宅局通知「配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について」(平成16年3月31日国住総第191号)に定める別記様式1「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」により受けている方で、当該確認書による相談の受付から5年を経過していない方(関係機関の「公営住宅への入居等に関する配偶者暴力被害申出受理確認書」が必要)。
2.世帯の条件を満たす方
2人以上の世帯の場合、次のア~ウのいずれかに該当している世帯
ア.夫婦・親子である世帯(夫婦は住民票上の内縁関係並びに西宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度及び兵庫県パートナーシップ制度に基づくパートナー関係を含む。住民票上の内縁関係の方は、住民票で夫(未届)・妻(未届)が記載されており、かつ、戸籍謄本で他に婚姻関係がないことが確認できる世帯。西宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度及び兵庫県パートナーシップ制度に基づくパートナー関係はパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた世帯で、かつ、戸籍謄本で他に婚姻関係がないことが確認できる世帯。)
※募集開始日現在、出生していない胎児は、申込書の記入にあたり「入居する者」には含むことはできません。
イ.婚約中(住民票上の内縁関係並びに西宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明制度及び兵庫県パートナーシップ制度に基づくパートナー関係を含む)であり各募集ごとに定められた期日までに入籍等を行い、それを証明する公的書類を提出でき、同時に入居できること。万一、期日までに入籍等できない場合は、失格となり、鍵をお渡しできません。また、申込後に婚約者等が変わったときは失格となります。
ウ.3親等以内の親族で、募集開始日現在、現に居住地を一つにしており、そのことを住民票等で証明できる世帯。
※以下のような不自然な家族の合併・分割をした申し込みは一切できません。
下記に該当しない場合でも、申し込みができない場合があります。
- 夫妻(内縁等を含む)が別々に居住することを前提に申し込むこと。
(例:夫婦の長期別居、離婚調停中または協議中であっても、募集開始日現在、離婚が成立していなければ一方だけの申し込みはできません。ただし、上記(B)に規定するDV被害者を除きます。) - 現在、別居している兄弟・姉妹・祖父母・その他親族をよびよせて申し込むこと。
- 扶養義務のある親がいるのにもかかわらず、その子が他の者と同居する場合など。
- 18歳未満の兄弟姉妹のみで申し込むこと。
3.収入基準にあう方(入居予定者全員の収入合計が対象です。)
「政令月収の計算方法」を参考として収入基準に合うかどうか確かめてください。
普通市営住宅
計算後の政令月収額(世帯合算)が158,000円以下の方が申し込むことができます。
※計算後の政令月収額(世帯合算)が158,000円を超える方でも「裁量階層世帯」に該当する方は、計算後の政令月収額(世帯合算)が214,000円以下であれば申し込むことができます。
特定公共賃貸住宅
計算後の政令月収額(世帯合算)が158,000円以上で487,000円以下の方が申し込むことができます。
※計算後の政令月収額(世帯合算)が139,000円以上158,000円未満である世帯にあっては収入のある世帯員のうちに35歳以下の方がいれば申し込むことができます。
※所得のある方が一人で、所得の種類が一種類で、特別控除対象者のいない世帯の方は「収入基準早見表」を参考にしていただくと簡単に収入基準に合うかどうかがわかります。
リンク
4.現在、住宅に困窮している方
持家の方は原則として申し込むことができません。ただし、市営住宅入居時までに申込者及び市営住宅に入居しようとする者以外に所有権を移転されるなど、処分を予定している場合には申し込むことが出来ます。
住宅困窮理由に該当する方
- 災害の危険があるような半壊住宅やバラックに住んでいる。
- 他の世帯と同居していて、便所または炊事場が共同である。
- 住宅がないため親族と別居している。
- 急な坂道にある住宅に住んでいる。
- 部屋がせまい。(1人あたり4.5帖以下)
- 正当な立退き要求を受けているが、立退き先がない(家賃の不払い等自己の責めに帰する場合を除く)。
- 通勤に片道1時間半以上かかる。
- 収入と比較して家賃が高すぎる。
- 婚約しているが、住宅がないため結婚がのびている。
- その他客観的にみて、上記のいずれかと同じような理由により住宅に非常に困っている。
5.入居予定者全員が暴力団員でないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である者が入居予定者にいる場合申し込みできません。
※暴力団員であるか否か警察等に照会し、調査することがありますので、同意される方のみ申し込みしてください。なお、申し込みされた方は、同意したものとみなします。
6.募集期間最終日現在、申込者が成年(18歳以上)であること。
市営住宅の募集について
市営住宅の募集時期等については、
『市営住宅の募集について』をご覧ください。