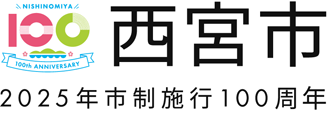おおた先生のわくわくだより
更新日:2025年12月2日
ページ番号:66847807

おおた先生のプロフィール
太田 秀紀(おおた ひでき)
日本小児科学会認定小児科専門医
日本小児心身医学会認定子どもの心の専門医
【専門分野】発達障害、心身症、重症心身障害児医療
【趣味】音楽鑑賞(主に洋楽ロックなど)
第50回 「 “社会モデル”という視点」
「スクールソーシャルワーカー(以下SSW)」という職種があることを知っていますか?
SSWとは学校における児童生徒を取り巻く環境に働きかけることにより、
子どもたちが抱える問題を解決すべく支援を行う専門職です。
学校の先生にとっては馴染みある存在かと思いますが、一般には知らない人も多いのではないでしょうか
(実は私もこども未来センターで働き始めるまで知りませんでした)。
「学校における福祉の専門家」のように紹介されることもありますが、発達障害等への理解(医学)・
子どもの心の理解(心理学)・子どもの権利やインクルージョンへの理解(社会学)といった多分野への知識をもとに、
子どもが安心して学校で過ごせるための環境調整を担います。
SSWは「社会モデル」という考え方を大切にしています。
これは「個人モデル(医学モデルともいわれる)」に対比した考え方です。
一例を示します。
車いすの方が階段を前にした際、「個人モデル」での“障害”はその方の「身体」にあると考えます。
もし身体だけに原因があるとすると、この方は自力でなんとかしないといけないということになってしまいます。
「社会モデル」の考えでは「階段」という環境を“障害”とみなし、問題解決のためにはスロープの設置や
エレベーターをつける(環境調整)ことが真に必要な支援である、となるわけです。
学校において、ある児童に問題(に見えること)が発生した時、例えばAくんが教室で暴れているとしましょう。
「個人モデル」の考えでは、Aくん個人の原因に注目します。医療機関の受診を勧められ発達障害の有無を調べることは、
見かたによっては「個人モデル」的発想の対応とも言えます(これはこれで必要なことではあります)。
しかし、これだけでは問題解決には不十分です。
理解を誤ると「Aくんは困った子」・「原因はAくん」という偏った認識にもなりかねません。
「社会モデル」の考えでは、Aくん個人の原因について正しく理解するとともに、
「暴れざるを得ない背景(困っているのはAくん、という発想)」を考察します。
実はAくんは特定の児童からの“煽り”のような言動に耐えられなかったようです。
また音への過敏性があり、教室が騒がしいと不安定になるのでした。
そこで、Aくんに限らず教室にいる全員(先生も含む)が安心して過ごせるように、
他の児童への指導や教室環境の調整が行われました。
このような「誰も排除しない・皆が安心できる」ことを目的とした問題解決思考が「社会モデル」です。
家庭や集団活動での子どもの言動に「困ったな、、」と思った時、「社会モデルの視点」を思い出してください。
解決のヒントが得られると思います。
<参考図書>
こども未来センターの同僚でもあるスクール/子どもソーシャルワーカーの小谷綾子さんの著書
「包摂する教室(明治図書)」では、「社会モデル」について分かりやすく、かつ実践的に書かれています。
「子どもの権利」・「不登校・児童虐待・ヤングケアラー」等昨今の子どもにまつわる話題についても解説されています。
子どもに関わる支援者・保護者にとってとても参考になると思います。