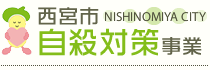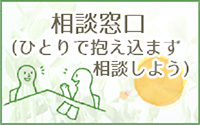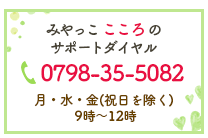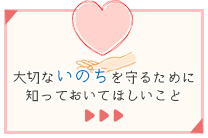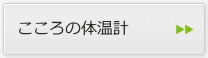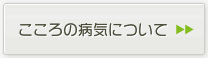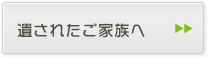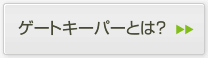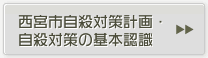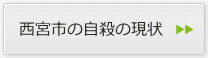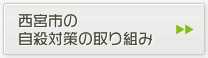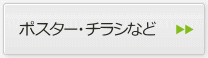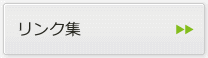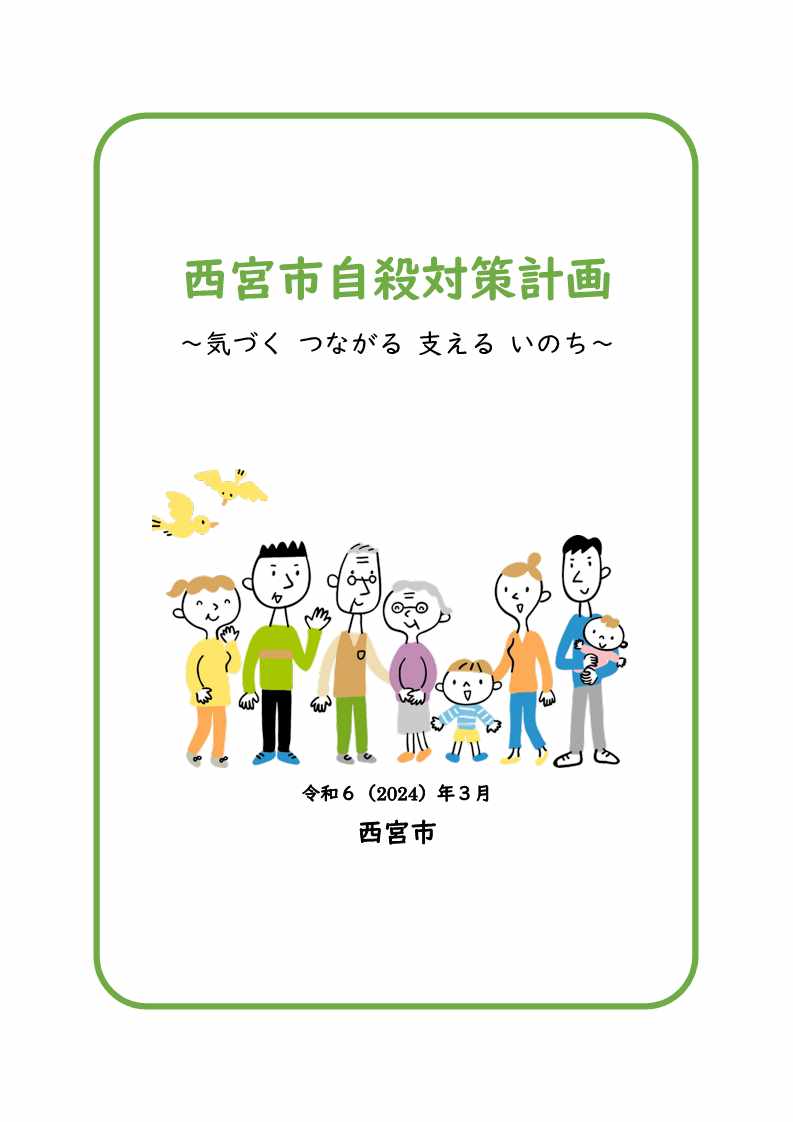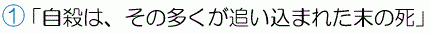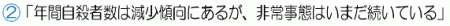「西宮市における自殺対策計画」について 
西宮市では「新・にしのみや健康づくり21(第2次)西宮市健康増進計画」の中に自殺対策計画を包含し、自殺対策に取り組んできましたが、令和6年3月に「西宮市自殺対策計画」を策定することで、庁内及び関係機関・団体等の連携を強化し、自殺対策のより一層の推進を目指します。
西宮市自殺対策計画
「自殺対策基本法」「自殺総合対策大網」について
日本の自殺死亡率は先進諸国と比較して高い水準にあり、特に、バブル崩壊後の平成10年以降は3万人を超えていました。日本では平成18年6月に自殺対策基本法が成立し、平成19年6月に自殺総合対策大綱が閣議決定され、国を挙げて総合的な取り組みが実施されました。結果、自殺対策基本法が成立した平成18年と、コロナ禍以前の令和元年の自殺者数を比較すると、男性が38%女性は35%減少し、これまでの取組に一定の効果があったと考えられます。しかし、長引くコロナ禍の影響により、自殺の要因となる様々な問題が悪化し、女性・小中高生は過去最多の水準となっています。令和4年10月には新たな自殺総合対策大綱が閣議決定され、コロナ禍の自殺動向も踏まえ総合的な自殺対策の更なる推進・強化が進められています。
自殺総合対策における基本認識(旧自殺総合対策大綱)
自殺は、人が自ら命を絶つ瞬間的な行為としてだけでなく、人が命を絶たざるを得なかった状況に追い込まれるプロセスとして捉える必要がある。
自殺行動に至った人の直前の心の健康状態を見ると、大多数は様々な悩みにより心理的に追い詰められた結果、抑うつ状態であったり、うつ病、アルコール依存症等の精神疾患を発症していることが明らかになっている。
このように、個人の自由な意思や洗濯の結果ではなく、「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」ということができる。
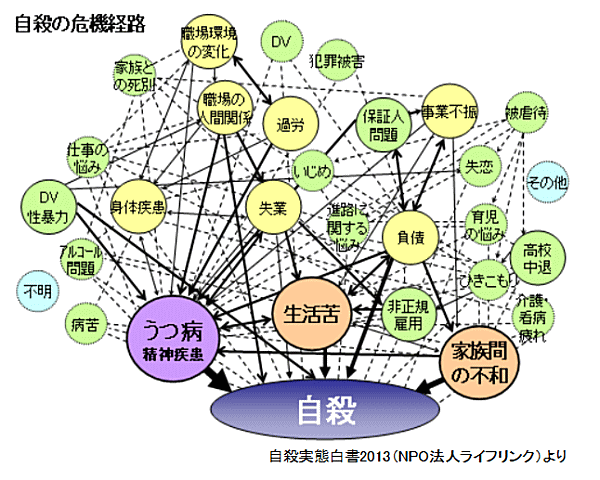
年間自殺者数は、平成22年以降7年連続で減少し、人口10万人当たりの自殺による死亡率は着実に低下している。しかし、20歳未満の自殺死亡率が、平成10年以降おおむね横ばいであることに加え、20歳代や30歳代における死因の第一位が自殺であり、
自殺死亡率も他の年代に比べて、ピーク時からの減少率が低く、非常事態はいまだ続いていると言わぜるをえない。
さらに、我が国の自殺死亡率は主要先進7か国の中で最も高く、かえがえのない多くの命が日々、自殺に追い込まれている状態である。
基本法が、施行から10年の節目に改正され、都道府県及び市町村は、大綱及び地域の実情等を勘案して、地域自殺対策計画を策定するものとされた。あわせて、国はそれを支援するため、自殺総合対策推進センターにおいて、都道府県及び市町村を自殺の地域特性ごとに類型化し、
それぞれにおいて実施すべき自殺対策事業をまとめた政策パッケージを提供すること、そして実施した成果等を分析し、分析結果を踏まえて改善を図る、そうすることにより、より精度の高い政策パッケージを地方公共団体に還元することとなる。
このように、自殺総合対策は国と地方公共団体等が協力しながら、全国的なPDCAサイクルを通じて、自殺対策を常に進化させ推進していく取組である。